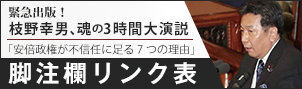発達障害者とともに働く人へ。ADHD当事者の私が提案する4つのステップ。
 「で? 改善の見込みはあるの?」
発達障害をカミングアウトして最初に上司から告げられた一言だった。
「注意欠陥ナントカはうちの職種には向かないよ」
私は大学を卒業してから、最初の就職先を2年弱で実質的にクビになり、次の就職先でも1年ももたずに他社に出向することとなった。理由ははっきりしている。信じられないほどに、ミスが多いということだった。
そうした中で、私は社会人2年目でADHD(注意欠陥多動性障害)と社会コミュニケーション障害(※1)の診断を受け、いまでは職場の一部の人に限定してADHDをオープンにして働いている。読者のなかには、職場で発達障害を持つ人を「活用」するのに難しさを感じている方もいるだろう。この記事では、ADHDを職場でカミングアウトした個人的な経験から、発達障害を持つ人たちに職場でどのように接するべきか考えていきたい。
(※1)ASD(自閉症スペクトラム、アスペルガー症候群)と似たコミュニケーションの障害だが、ASDのような興味の偏りや反復的行動は伴わない
「で? 改善の見込みはあるの?」
発達障害をカミングアウトして最初に上司から告げられた一言だった。
「注意欠陥ナントカはうちの職種には向かないよ」
私は大学を卒業してから、最初の就職先を2年弱で実質的にクビになり、次の就職先でも1年ももたずに他社に出向することとなった。理由ははっきりしている。信じられないほどに、ミスが多いということだった。
そうした中で、私は社会人2年目でADHD(注意欠陥多動性障害)と社会コミュニケーション障害(※1)の診断を受け、いまでは職場の一部の人に限定してADHDをオープンにして働いている。読者のなかには、職場で発達障害を持つ人を「活用」するのに難しさを感じている方もいるだろう。この記事では、ADHDを職場でカミングアウトした個人的な経験から、発達障害を持つ人たちに職場でどのように接するべきか考えていきたい。
(※1)ASD(自閉症スペクトラム、アスペルガー症候群)と似たコミュニケーションの障害だが、ASDのような興味の偏りや反復的行動は伴わない
そもそも、発達障害とは?
ハッシュタグ