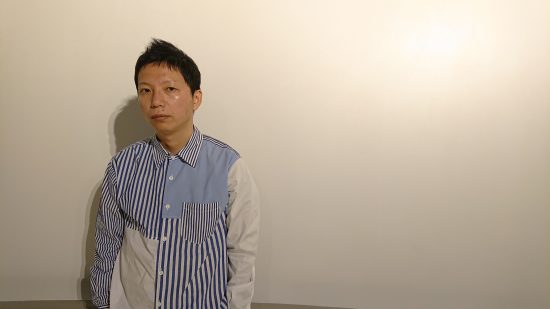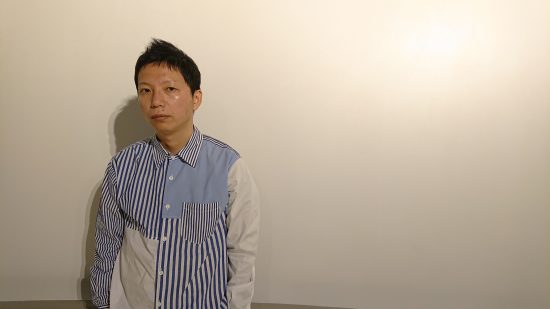――映画作りにあたっては、出演を希望する中学生を対象にワークショップをやったそうですね。
内藤:映画を作るにあたっては役者とじっくり話し合いたかったんです。また、子ども達の視点、見え方を映画に取り入れたいという気持ちもありました。ワークショップは全8回やりましたが、彼らの中から出てきたアイデアを脚本や演出に取り入れてきました 。
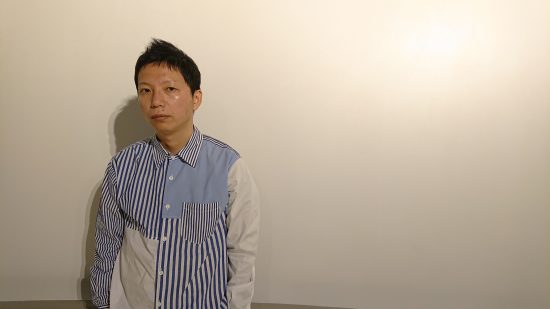
内藤瑛亮監督
具体的には、いじめの事件の内容を伝えたり、いじめのロールプレイも行いました。抽象的な名前を付けて罵倒するんです。例えば、ある人にアイスクリームという名前をつけたら、「甘いんだよ」とか「溶けるんじゃねーよ」という言葉を投げ掛けます 。
当然、その場はきついフレーズで言った方が盛り上がります。そして、その場は笑いの溢れる楽しい場にはなるのですが、冷静になって考えてみると、人を罵倒することで喜びを感じていたことを自覚します。
そこで誰もが加虐性を持っているということに気が付くんですね。そして、いじめている側にとって「いじめ」は単なるエンターテイメントということも認識します。そうしたことをワークショップで体感してもらって、撮影現場では、演出につなげていきました。
加害者家族と被害者家族がばったり会って加害者が被害者に謝るというシーンも、ワークショップでの意見を取り入れました。花束を何回投げつけられても取りに行ったり、土下座しても無理やり立たされたり。そういうアイデアを取り入れることで映画が豊かになっていきました 。
――この映画は商業映画としての公開も試みたとのことでしたが、最終的には自主映画として公開されることになりました。自主映画として製作するまでの経緯についてお聞かせください。
内藤:いくつか企画を製作会社に持ち込みましたが、「もっとエンターテイメントにして欲しい」という要望があったり、「20歳過ぎの人でもアイドルやネームバリューのある人を使えば可能性はあるね」と言われました。そもそも反応がなかったということもありました。
興味を持ってくれた方はいましたが、 自分の望む形で製作は難しいと判断しました。そこで、自主製作の形を取ることにして、自分の出資で製作をスタートしたところ、協力してくれるプロデューサーや製作会社が現われました。ちなみに、この作品は助成金やクラウドファンディングによるサポートは受けていません。
――自主映画の製作に不可欠と言われる助成金のあり方についてはどのようにお考えでしょうか。
内藤:助成される作品は無難な題材になってしまうということが問題だと思います。例えば、韓国では政府が多種多様な作品に助成を続け、ついに『パラサイト 半地下の家族』のように、アジアで初のアカデミー賞受賞という快挙を成し遂げています。
日本では、撮影現場を借りることですら難しいという現実があり、全体的に映画製作に対する支援が難しいので、助成も無難な作品になってしまっているのではないでしょうか。
日本政府は今、芸術文化に対する理解を問われていると思います。コロナでエンタメ業界への補償のなさを見ると芸術に対する理解のなさを目の当たりにした気持ちになります。ドイツが「アーティストは今、生命維持に必要不可欠な存在」というスタンスで支援して補償も払ったことに対し、日本は理解のなさがより残酷な形で明確になった気がしますね。