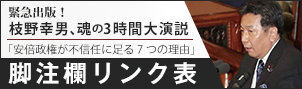「カリスマ」の来た道――シリーズ【草の根保守の蠢動 第28回】
安東巌はどこから来たのか?
 村上正邦は「安東巌は若手のリーダー格と目されていた」と言明し、魚住昭はそれをはっきりと記録に残している。
この事例以外、一般書籍で安東巌の名前を見つけることは難しい。やはり教団の出した出版物を確認するしかないだろう。
各方面を探すうち、彼が書いたと思われる書籍を見つけた。発行は「生長の家青年会中央部」とある。
奥付には、安東巌の詳細な経歴が書かれていた。
“安東巌
昭和14年佐賀県鳥栖市に生まれる。9年間病に臥すも、『生命の実相』に触れ、病床より決然と起ち上がる。25歳で高校に復学し、27歳で長崎大学に入学する。当時学園紛争の最中にあった長崎大学の正常化を決意し、国立大学で初の民族派による自治会争奪を成し遂げ、連続三期自治会を掌握する。
昭和45年生長の家本部青年局に奉職し、同47年青年会中央事務局長となり、森田中央執行委員長(現、青年会会長)の下、『理想世界』百万部運動を推進する。同50年青年会副会長を経て、現在政治局政治部長。”
とある。
この書籍が出版されたのは、昭和55 年。つまり1980年。「生長の家」が政治運動から撤退するわずか3年前のこと。そして、日本青年協議会が初めて「大人の運動」を遂行し見事な成果を上げた「元号法制化運動」が結実した1979年の翌年に当たる。「生長の家政治運動」がその頂点を極めていた頃だ。そのタイミングで、「政治局政治部長」という政治運動の最要職にいた男が、安東巌だということになる。
この経歴には、極めて重要なキーワードがちりばめられている。「9年間の病臥の後『生命の実相』に触れ復活」「27歳で高校に復学」「長崎大学学園正常化運動」「『理想世界』百万部運動」等々。
この一つ一つのキーワードが、安東巌をカリスマたらしめている。
次回、安東巌を知る人々の証言をもとに、いかにして彼がカリスマを持つに至ったか、そしてそれをどう保持しているかを紐解いていこう。
※1日本学生同盟。持丸博をはじめとし、初期の「楯の会」に多数の活動家を輩出した。日学同こそがあの時代、民族派学生運動にロジックと運動スタイルを持ち込んだとも言える。本連載は必然的に全国学協に軸足を置かざるをえないので、日学同の思想や運動について言及できないが、いずれ機会があれば、彼らについても書きたい。
※2三島事件を挟んだ前後の動向は今日から見て極めて重要な意味を持つ。日学同・全国学協のみならず、実にたくさんの人々が三島事件の前後に自分自身の運動の再総括に迫られて運動の色彩を変えていった。その余波がまだ今日まで続いているのだ。この点についても機会があれば改めて詳細に書きたい
(参考文献)
安東巌,1980『わが思い ひたぶるに』生長の家青年会中央部.
魚住昭,2007『我、国に裏切られようとも:証言村上正邦』講談社.
<取材・文/菅野完(Twitter ID:@noiehoie) photo by photo by Michał Kulesza(CC0 PublicDomain) photo by 本屋 on Wikimedia Commons(CC BY-SA 3.0) >
村上正邦は「安東巌は若手のリーダー格と目されていた」と言明し、魚住昭はそれをはっきりと記録に残している。
この事例以外、一般書籍で安東巌の名前を見つけることは難しい。やはり教団の出した出版物を確認するしかないだろう。
各方面を探すうち、彼が書いたと思われる書籍を見つけた。発行は「生長の家青年会中央部」とある。
奥付には、安東巌の詳細な経歴が書かれていた。
“安東巌
昭和14年佐賀県鳥栖市に生まれる。9年間病に臥すも、『生命の実相』に触れ、病床より決然と起ち上がる。25歳で高校に復学し、27歳で長崎大学に入学する。当時学園紛争の最中にあった長崎大学の正常化を決意し、国立大学で初の民族派による自治会争奪を成し遂げ、連続三期自治会を掌握する。
昭和45年生長の家本部青年局に奉職し、同47年青年会中央事務局長となり、森田中央執行委員長(現、青年会会長)の下、『理想世界』百万部運動を推進する。同50年青年会副会長を経て、現在政治局政治部長。”
とある。
この書籍が出版されたのは、昭和55 年。つまり1980年。「生長の家」が政治運動から撤退するわずか3年前のこと。そして、日本青年協議会が初めて「大人の運動」を遂行し見事な成果を上げた「元号法制化運動」が結実した1979年の翌年に当たる。「生長の家政治運動」がその頂点を極めていた頃だ。そのタイミングで、「政治局政治部長」という政治運動の最要職にいた男が、安東巌だということになる。
この経歴には、極めて重要なキーワードがちりばめられている。「9年間の病臥の後『生命の実相』に触れ復活」「27歳で高校に復学」「長崎大学学園正常化運動」「『理想世界』百万部運動」等々。
この一つ一つのキーワードが、安東巌をカリスマたらしめている。
次回、安東巌を知る人々の証言をもとに、いかにして彼がカリスマを持つに至ったか、そしてそれをどう保持しているかを紐解いていこう。
※1日本学生同盟。持丸博をはじめとし、初期の「楯の会」に多数の活動家を輩出した。日学同こそがあの時代、民族派学生運動にロジックと運動スタイルを持ち込んだとも言える。本連載は必然的に全国学協に軸足を置かざるをえないので、日学同の思想や運動について言及できないが、いずれ機会があれば、彼らについても書きたい。
※2三島事件を挟んだ前後の動向は今日から見て極めて重要な意味を持つ。日学同・全国学協のみならず、実にたくさんの人々が三島事件の前後に自分自身の運動の再総括に迫られて運動の色彩を変えていった。その余波がまだ今日まで続いているのだ。この点についても機会があれば改めて詳細に書きたい
(参考文献)
安東巌,1980『わが思い ひたぶるに』生長の家青年会中央部.
魚住昭,2007『我、国に裏切られようとも:証言村上正邦』講談社.
<取材・文/菅野完(Twitter ID:@noiehoie) photo by photo by Michał Kulesza(CC0 PublicDomain) photo by 本屋 on Wikimedia Commons(CC BY-SA 3.0) >すがのたもつ●本サイトの連載、「草の根保守の蠢動」をまとめた新書『日本会議の研究』(扶桑社新書)は第一回大宅壮一メモリアル日本ノンフィクション大賞読者賞に選ばれるなど世間を揺るがせた。メルマガ「菅野完リポート」や月刊誌「ゲゼルシャフト」(sugano.shop)も注目されている
 |
『日本会議の研究』 「右傾化」の淵源はどこなのか?「日本会議」とは何なのか? 
|
前回の記事
ハッシュタグ