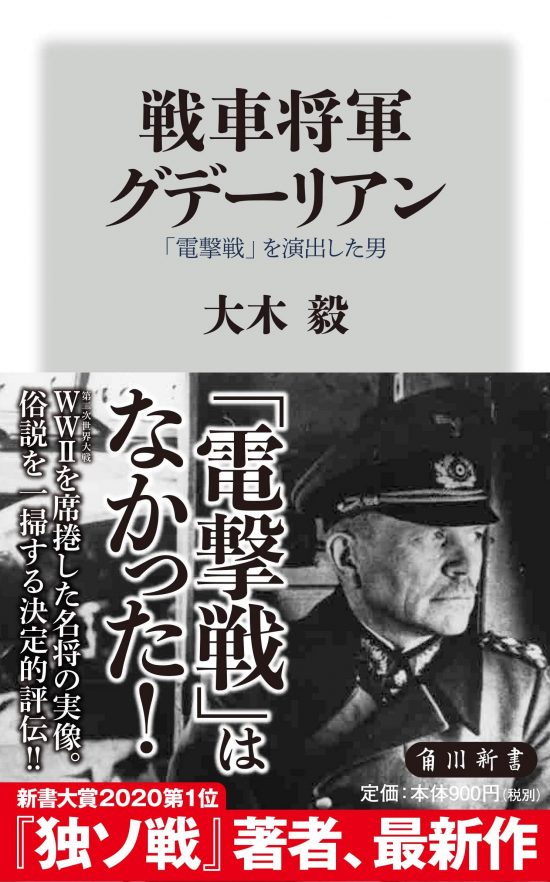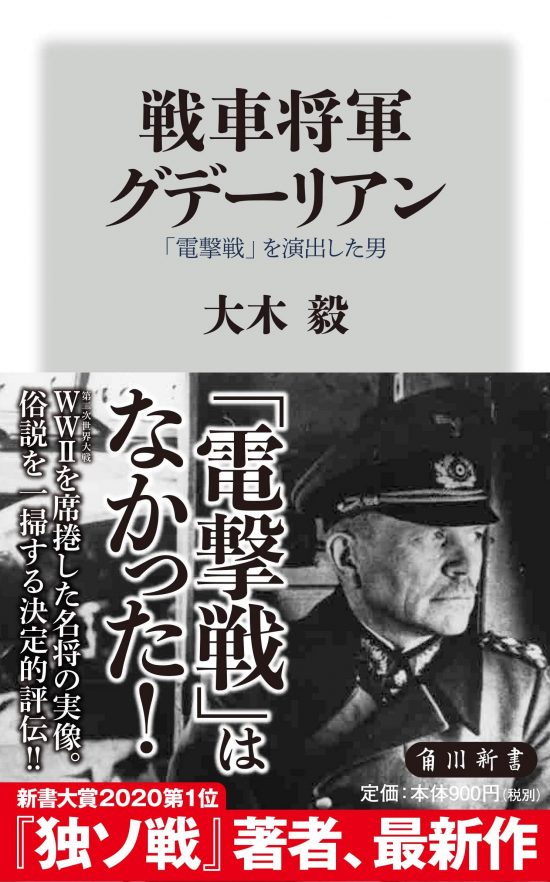―― 『戦車将軍グデーリアン』で興味深いのは、ヒトラーと軍人たちの関係です。実はヒトラーはグデーリアンたちに色々と気を使っていました。
大木:ヒトラー政権は1933年1月30日に成立しますが、当時は連立政権で、すべての閣僚がナチ党に属していたわけではありません。また、
国防軍、とりわけ陸軍はプロイセンの時代から非常に自立性が強く、必ずしもヒトラーの言いなりだったわけではありません。
たとえば、1937年にヒトラーは秘密会議を開き、数年のうちにオーストリアとチェコスロヴァキアを征服すると明言しました。それに対して、国防相にして国防軍最高司令官だった
ブロンベルク元帥と陸軍総司令官
フリッチュ上級大将が疑義を唱えました。その後、彼らはスキャンダルをきっかけに職を退きますが、ヒトラーの命令一下で国防軍が一枚岩で動いたわけではないのです。
私の見解では、ヒトラーが国防軍を掌握できたのは、
1944年7月20日にヒトラー暗殺未遂事件が起こったあとです。ヒトラーは事件に関与した軍人たちを強制収容所に送り込んだり、処刑したりしました。あれは一種のカウンタークーデターで、これでようやく国防軍に対する支配が完成したと言えます。
―― イギリスの歴史家であるイアン・カーショーは、ナチスの権力構造は非常に複雑で入り組んでいたと指摘しています。国防軍内の権力構造はどうだったのでしょうか。
大木:それは軍隊にも当てはまります。たとえば、西部戦線の大規模団隊の一つであるA軍集団参謀長に配置されていた
マンシュタイン中将は、
ハルダー陸軍参謀総長や
ブラウヒッチュ陸軍総司令官に自らの作戦案を拒否されると、ヒトラー付の国防軍首席副官に働きかけ、ハルダーやブラウヒッチュを迂回して総統に直談判しています。国防軍内部でもこうしたことが起こっていたのです。
―― 戦後の日本にとって軍事史はまだまだ身近な存在とは言えません。いま軍事史を学ぶ意義をどのように考えていますか。
大木:最初に述べたように、
戦後の日本では戦争は知らなくてもいいものとされてきました。実際、戦争が起きる蓋然性はとても低かったため、戦争について学ばなくても大きな問題はありませんでした。
しかし、最近は戦争は身近なものになっており、朝鮮半島にしろ南西方面にしろ、
戦争が起こる蓋然性が大きくなっています。私の本を手にとってくれる方々も、皮膚感覚でそのことを実感しているのだと思います。戦争や軍事に関する知識への欲求、その欠如を埋めてほしいという社会的要求が高まっているように感じます。
一部には、戦争のことを知るとまた戦争をしたくなるといった議論がありますが、
戦後の日本でもある一時期までは、左翼こそクラウゼヴィッツなどの研究に取り組んでいました。トロツキーは「
君は戦争に関心がないかもしれないが、戦争のほうは君に関心を持っている」と言っています。
戦争を避けるためにこそ、軍隊や戦争について学ばなければならないと思います。
(3月27日、聞き手・構成 中村友哉)
大木毅●おおき・たけし。1961年東京生まれ。立教大学大学院博士後期課程単位取得退学。DAAD(ドイツ学術交流会)奨学生としてボン大学に留学。千葉大学その他の非常勤講師、防衛省防衛研究所講師、陸上自衛隊幹部学校講師などを経て、現在著述業。『
独ソ戦 絶滅戦争の惨禍』(岩波新書)で新書大賞2020大賞を受賞。主な著書に『
「砂漠の狐」ロンメル ヒトラーの将軍の栄光と悲惨』(角川新書)、『
ドイツ軍事史』(作品社)などがある。
げっかんにっぽん●Twitter ID=
@GekkanNippon。「日本の自立と再生を目指す、闘う言論誌」を標榜する保守系オピニオン誌。「左右」という偏狭な枠組みに囚われない硬派な論調とスタンスで知られる。