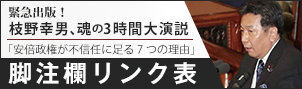香港の若者たちはなぜまだ立ち上がれるのか? 彼らを支えた「ツール」<日本人がまだ知らない香港デモの実像>
熟議を深めるアプリの存在も
合理性と非合理性のはざまで
 しかし、いくらツールが発達していても結局、それを使いこなすのは人間である。ある30代の香港人女性Cの言葉にヒントがあった。
「私たちの世代は小学校の授業からExcelを学んできたし、個人的にはPhotoshopも小学校から使っていた。そういう人は多いと思う」
1995年、私が中学生の頃、Windows95の発売があった。あれから25年。日本ではインターネットを「消費」に使う発想がいまだに主流だが、香港ではネット黎明期から「生産」のために使うという教育がなされてきたようだ。それは金融を経済の主柱とした都市国家として本寸法の道筋であったのだろう。子供の頃からExcelやPhotoshopを使うことは、実際にその技術を習得するというメリット以上に、優先順位、プライオリティを選び取る力、合理的な取捨選択能力の基礎を育んだのでははないだろうか?
いきなり古い話になるが、1954年の名画、黒澤明監督の『七人の侍』のなかに、「野伏せり来るだぞ!首が飛ぶつうのに、ヒゲの心配してどうするだ!」というセリフがある。野武士の襲来を前に、小さなことで狼狽える村民を長老が一喝する名台詞である。これは共同体としてのプライオリティを考え行動せよ。という目的達成のための原理原則を捉えた名シーンだ。実は私自身、この3年、日本国内のいくつかのリベラル陣営の選挙を見つめたが、このセリフを引用したくなる場面に多々遭遇した。
優先順位を意識し行動する。日本のリベラル陣営が「正しさ」という驕りとともに忘れがちな行動原理を香港のプロテスターたちは適切に育んでいたのだ。
<取材・文・撮影/大袈裟太郎>
しかし、いくらツールが発達していても結局、それを使いこなすのは人間である。ある30代の香港人女性Cの言葉にヒントがあった。
「私たちの世代は小学校の授業からExcelを学んできたし、個人的にはPhotoshopも小学校から使っていた。そういう人は多いと思う」
1995年、私が中学生の頃、Windows95の発売があった。あれから25年。日本ではインターネットを「消費」に使う発想がいまだに主流だが、香港ではネット黎明期から「生産」のために使うという教育がなされてきたようだ。それは金融を経済の主柱とした都市国家として本寸法の道筋であったのだろう。子供の頃からExcelやPhotoshopを使うことは、実際にその技術を習得するというメリット以上に、優先順位、プライオリティを選び取る力、合理的な取捨選択能力の基礎を育んだのでははないだろうか?
いきなり古い話になるが、1954年の名画、黒澤明監督の『七人の侍』のなかに、「野伏せり来るだぞ!首が飛ぶつうのに、ヒゲの心配してどうするだ!」というセリフがある。野武士の襲来を前に、小さなことで狼狽える村民を長老が一喝する名台詞である。これは共同体としてのプライオリティを考え行動せよ。という目的達成のための原理原則を捉えた名シーンだ。実は私自身、この3年、日本国内のいくつかのリベラル陣営の選挙を見つめたが、このセリフを引用したくなる場面に多々遭遇した。
優先順位を意識し行動する。日本のリベラル陣営が「正しさ」という驕りとともに忘れがちな行動原理を香港のプロテスターたちは適切に育んでいたのだ。
<取材・文・撮影/大袈裟太郎> ハッシュタグ