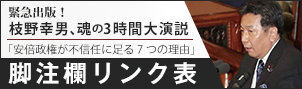私たちは人種や移民に関する偏見をどう問い直せばよいのか
SNSで起こるエコーチェンバー現象

荻上チキさん
メディアがコミュニケーションの文脈をどう作っていくかが大切
 また、能動的な人がSNSで積極的に意見を述べる一方で、受動的な人にはどう関連性を与えられるかについても、セッションで議題に上がった。
荻上氏は、「受動的な人にはどうバイアスを自覚してもらうかだと思う。それはネットでの言論がクラスタ化している事実はあるものの、何を議題にするかによって意見の仕方が変わってくるからである。人はオピオニンリーダーをジャンルごとに横断的に決め、言葉やアジェンダなどの情報を取り入れている。 論点として接触する機会が増えれば、どういう議題が世の中で上がっていて、こういう文脈で語れば良いのではというフレーミングをする。メディアが事実をもとにどうコミュニケーションの文脈を作っていくかがいつの時代も大事」と説明した。
感情接触や知識の蓄積だけではバイアスが減るわけではない。しかし、バイアスは今の状況を肯定する考え方だという。
セッションを通して語られた暴力やマイノリティへの偏見、差別、インターネットの言論空間など様々な事象には、バイアスが存在している。そのバイアス自体を取り除くのではなく、再定義すること。すなわち、既存の社会的フレームに収めるのではなく、見方を変えてリフレームすることが、これからの現代社会を生き抜くヒントになるのではないか。
<取材・文/古田島大介>
また、能動的な人がSNSで積極的に意見を述べる一方で、受動的な人にはどう関連性を与えられるかについても、セッションで議題に上がった。
荻上氏は、「受動的な人にはどうバイアスを自覚してもらうかだと思う。それはネットでの言論がクラスタ化している事実はあるものの、何を議題にするかによって意見の仕方が変わってくるからである。人はオピオニンリーダーをジャンルごとに横断的に決め、言葉やアジェンダなどの情報を取り入れている。 論点として接触する機会が増えれば、どういう議題が世の中で上がっていて、こういう文脈で語れば良いのではというフレーミングをする。メディアが事実をもとにどうコミュニケーションの文脈を作っていくかがいつの時代も大事」と説明した。
感情接触や知識の蓄積だけではバイアスが減るわけではない。しかし、バイアスは今の状況を肯定する考え方だという。
セッションを通して語られた暴力やマイノリティへの偏見、差別、インターネットの言論空間など様々な事象には、バイアスが存在している。そのバイアス自体を取り除くのではなく、再定義すること。すなわち、既存の社会的フレームに収めるのではなく、見方を変えてリフレームすることが、これからの現代社会を生き抜くヒントになるのではないか。
<取材・文/古田島大介>1986年生まれ。立教大卒。ビジネス、旅行、イベント、カルチャーなど興味関心の湧く分野を中心に執筆活動を行う。社会のA面B面、メジャーからアンダーまで足を運び、現場で知ることを大切にしている。
1
2
ハッシュタグ