『新潮45』が生み出された社会。~反戦後民主主義者の主戦場となっている書店の平台
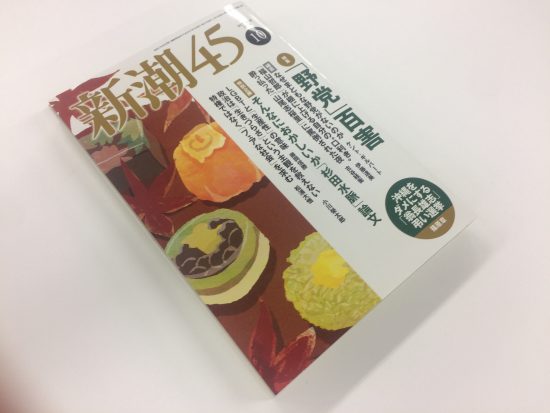 新潮社は、LGBTへの差別と偏見を煽る『新潮45』10月号(9月発売)の特別特集記事への大きな非難を受け、9月25日に『新潮45』休刊を決めた。
発端は『新潮45』8月号(7月発売)に掲載された杉田水脈衆議院議員の文章に「LGBTには生産性がない」との表現があったことだ。これは多くに人々の顰蹙を買い、永田町の自民党本部は抗議をする人々に取り囲まれた。自民党は抗議に応えるかたちで杉田議員を指導したと発表。不十分な措置とは言え、自民党が杉田議員への自重を求める措置をとったことで杉田発言は一応の終息を見せるかに見えた。
が、同誌は10月号(9月発売)で「特別企画 そんなにおかしいか「杉田水脈」論文」と銘打つ特集を組み、一旦は沈静化した非難を再燃させた。非難の矛先は杉田議員を擁護した小川榮太郎氏の「政治は「生きづらさ」という主観を救えない」と題した文書へ向けられた。この文章は性的指向と性的嗜好を混同した俗悪極まりないものだ。非難は小川榮太郎個人にとどまらず、発行元の新潮社にも向けられた。
小田嶋隆氏は日経ビジネスオンラインの連載で、「新潮45はなぜ炎上への道を爆走したか」と題し、今回の事案が「総理案件」であったことを指摘している。確かに、杉田水脈衆議議員も小川榮太郎氏も安倍晋三総理と極めて近い関係を持っている。
また毎日新聞は今年4月に『新潮45』が2018年1月号から『WILL』や『HANADA』と言った極右雑誌と似通った内容になったことを報じている(参照:新潮45“右寄り”に活路 「部数減で炎上商法」指摘も 毎日新聞)。
ここでは『新潮45』10月号の特別企画が登場するまでの書店店頭を中心とした出来事を改めて辿ってみようと思う。
新潮社は、LGBTへの差別と偏見を煽る『新潮45』10月号(9月発売)の特別特集記事への大きな非難を受け、9月25日に『新潮45』休刊を決めた。
発端は『新潮45』8月号(7月発売)に掲載された杉田水脈衆議院議員の文章に「LGBTには生産性がない」との表現があったことだ。これは多くに人々の顰蹙を買い、永田町の自民党本部は抗議をする人々に取り囲まれた。自民党は抗議に応えるかたちで杉田議員を指導したと発表。不十分な措置とは言え、自民党が杉田議員への自重を求める措置をとったことで杉田発言は一応の終息を見せるかに見えた。
が、同誌は10月号(9月発売)で「特別企画 そんなにおかしいか「杉田水脈」論文」と銘打つ特集を組み、一旦は沈静化した非難を再燃させた。非難の矛先は杉田議員を擁護した小川榮太郎氏の「政治は「生きづらさ」という主観を救えない」と題した文書へ向けられた。この文章は性的指向と性的嗜好を混同した俗悪極まりないものだ。非難は小川榮太郎個人にとどまらず、発行元の新潮社にも向けられた。
小田嶋隆氏は日経ビジネスオンラインの連載で、「新潮45はなぜ炎上への道を爆走したか」と題し、今回の事案が「総理案件」であったことを指摘している。確かに、杉田水脈衆議議員も小川榮太郎氏も安倍晋三総理と極めて近い関係を持っている。
また毎日新聞は今年4月に『新潮45』が2018年1月号から『WILL』や『HANADA』と言った極右雑誌と似通った内容になったことを報じている(参照:新潮45“右寄り”に活路 「部数減で炎上商法」指摘も 毎日新聞)。
ここでは『新潮45』10月号の特別企画が登場するまでの書店店頭を中心とした出来事を改めて辿ってみようと思う。
すでに「表現弾圧」されていたリベラル系書籍
ハッシュタグ


