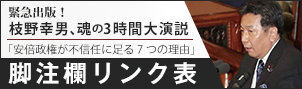子どもの権利を代弁する「アドボケイト」は、子どもの望みを叶えられるか?
「子どもの権利」に対する尊重は始まったばかり
 今年6月、児童福祉法の一部が改正され、附則に次のように書かれた。
「政府は、この法律の施行後二年を目途として、児童の保護及び支援に当たって、児童の意見を聴く機会及び児童が自ら意見を述べることができる機会の確保、当該機会における児童を支援する仕組みの構築、児童の権利を擁護する仕組みの構築その他の児童の意見が尊重され、その最善の利益が優先して考慮されるための措置の在り方について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする」(参照:厚生労働省)
この法律は「令和二年四月一日から施行する」ので、2022年3月31日までに「児童の最善の利益が優先して考慮されるための措置」が講じられる見込みだ。日本の児童福祉の現場では、親に虐待されるなどの事由によって保護や支援が必要になった児童自身の声を、これまで十分に尊重してこなかった。
今回の改正は、子どもの権利条約に批准している国として、以下の条約の内容に重い腰を上げて従った結果だろう。
【子どもの権利条約 第4条】
締約国は、この条約において認められる権利の実現のため、すべての適当な立法措置、行政措置その他の措置を講ずる。締約国は、経済的、社会的及び文化的権利に関しては、自国における利用可能な手段の最大限の範囲内で、また、必要な場合には国際協力の枠内で、これらの措置を講ずる。
では、改正児童福祉法に明記された「児童が自ら意見を述べることができる機会の確保」は、具体的にどういう形で実現するのか?
これについては今後2年間、文科省や厚労省の官僚が検討するのだろうが、「自国における利用可能な手段の最大限の範囲内」はまだ手探り状態だ。
たとえば、親に虐待されている子どもがいても、日本の子どもは、義務教育で虐待の定義を教わることもなければ、誰に相談できるのかも知らない。子ども自身が生き残るための必要不可欠な知識を教えられていないどころか、子どもの権利条約に明記された4つの権利をすらすら言える教師や校長、政治家、保護者も極めて珍しい。
今年6月、児童福祉法の一部が改正され、附則に次のように書かれた。
「政府は、この法律の施行後二年を目途として、児童の保護及び支援に当たって、児童の意見を聴く機会及び児童が自ら意見を述べることができる機会の確保、当該機会における児童を支援する仕組みの構築、児童の権利を擁護する仕組みの構築その他の児童の意見が尊重され、その最善の利益が優先して考慮されるための措置の在り方について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする」(参照:厚生労働省)
この法律は「令和二年四月一日から施行する」ので、2022年3月31日までに「児童の最善の利益が優先して考慮されるための措置」が講じられる見込みだ。日本の児童福祉の現場では、親に虐待されるなどの事由によって保護や支援が必要になった児童自身の声を、これまで十分に尊重してこなかった。
今回の改正は、子どもの権利条約に批准している国として、以下の条約の内容に重い腰を上げて従った結果だろう。
【子どもの権利条約 第4条】
締約国は、この条約において認められる権利の実現のため、すべての適当な立法措置、行政措置その他の措置を講ずる。締約国は、経済的、社会的及び文化的権利に関しては、自国における利用可能な手段の最大限の範囲内で、また、必要な場合には国際協力の枠内で、これらの措置を講ずる。
では、改正児童福祉法に明記された「児童が自ら意見を述べることができる機会の確保」は、具体的にどういう形で実現するのか?
これについては今後2年間、文科省や厚労省の官僚が検討するのだろうが、「自国における利用可能な手段の最大限の範囲内」はまだ手探り状態だ。
たとえば、親に虐待されている子どもがいても、日本の子どもは、義務教育で虐待の定義を教わることもなければ、誰に相談できるのかも知らない。子ども自身が生き残るための必要不可欠な知識を教えられていないどころか、子どもの権利条約に明記された4つの権利をすらすら言える教師や校長、政治家、保護者も極めて珍しい。
日本各地でも増え始めたアドボケイトの勉強会
1
2
ハッシュタグ