エイリアンの支配と傀儡政権への反抗を描くSF映画『囚われた国家』、より楽しむための「3つ」のポイント
2:クモの巣のような複雑な作劇にこそ意味がある

© 2018 STORYTELLER DISTRIBUTION CO., LLC. All Rights Reserved.
3:『猿の惑星:創世記』でもわかる“噛み合ってしまった歯車”から学べること
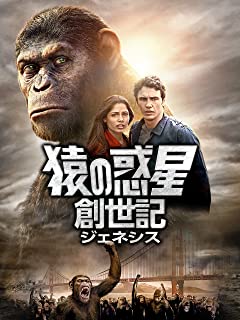 本作を手がけたルパート・ワイアット監督は、『猿の惑星:創世記(ジェネシス)』(2011)というハリウッド大作で高い評価を得ていた。こちらを観ておくと、より監督の作家性と物語の本質を知り、より『囚われた国家』が面白くなるということにも触れておきたい。
『猿の惑星:創世記』は、SF映画の古典『猿の惑星』(1968)の単なるリメイクではなく、そこから着想を得た“新たな物語”であり、新たな3部作の起点となった映画だ。関連作品を観ていなくても全く問題なく楽しめる、万人向けのエンターテインメントである。
その基本的なプロットは、高い知能を持つ猿が人間に育てられるが、ある出来事のせいで保護施設に送られてしまい、そこから何とかして脱走し、人間への反逆行為に転じていくというものだ。初めは“子育てもの”で、次は“脱獄もの”、そして『囚われた国家』と同様の“反抗ものSF”の要素までもある盛りだくさんな内容であり、誰もが次々に押し寄せる見せ場とサスペンスに圧倒されるだろう。
そして、『猿の惑星:創世記』および『囚われた国家』の劇中で起きている出来事の全てが、いくつかの歯車が“噛み合ってしまった”結果として起こっているということが重要だ。社会では様々な人物の思惑が複雑に交錯しており、それらが絡み合うと取り返しのつかない悲劇につながることもある……そんな普遍的な事実と、“起こりうる未来”を警告している。そもそもSF作品は完全な絵空事などではなく、現実の社会の先にある未来を描くことがほとんどなのだが、この2作ではそれが特に顕著なのである。
まるで、「こういう未来もあり得るから、こうならないように1人1人が何ができるか考えてみようよ」と、監督に問われているかのようだ。そうした内省を促してくれるということも『猿の惑星:創世記』と『囚われた国家』(およびSF作品全般)の大きな魅力であり、やはり現実の世界が大変である今にこそ観てほしいと思える理由なのだ。
ちなみに、その『猿の惑星:創世記』には、まさに恐ろしいウイルスがパンデミックする“兆し”も示されているという、今に観るとさらにタイムリーな要素もあったりする。配信サービスのHuluで、続編の『猿の惑星: 新世紀』(2014)と『猿の惑星: 聖戦記』(2017)も鑑賞できるので、ぜひ合わせて鑑賞してみてほしい。
<文/ヒナタカ>
本作を手がけたルパート・ワイアット監督は、『猿の惑星:創世記(ジェネシス)』(2011)というハリウッド大作で高い評価を得ていた。こちらを観ておくと、より監督の作家性と物語の本質を知り、より『囚われた国家』が面白くなるということにも触れておきたい。
『猿の惑星:創世記』は、SF映画の古典『猿の惑星』(1968)の単なるリメイクではなく、そこから着想を得た“新たな物語”であり、新たな3部作の起点となった映画だ。関連作品を観ていなくても全く問題なく楽しめる、万人向けのエンターテインメントである。
その基本的なプロットは、高い知能を持つ猿が人間に育てられるが、ある出来事のせいで保護施設に送られてしまい、そこから何とかして脱走し、人間への反逆行為に転じていくというものだ。初めは“子育てもの”で、次は“脱獄もの”、そして『囚われた国家』と同様の“反抗ものSF”の要素までもある盛りだくさんな内容であり、誰もが次々に押し寄せる見せ場とサスペンスに圧倒されるだろう。
そして、『猿の惑星:創世記』および『囚われた国家』の劇中で起きている出来事の全てが、いくつかの歯車が“噛み合ってしまった”結果として起こっているということが重要だ。社会では様々な人物の思惑が複雑に交錯しており、それらが絡み合うと取り返しのつかない悲劇につながることもある……そんな普遍的な事実と、“起こりうる未来”を警告している。そもそもSF作品は完全な絵空事などではなく、現実の社会の先にある未来を描くことがほとんどなのだが、この2作ではそれが特に顕著なのである。
まるで、「こういう未来もあり得るから、こうならないように1人1人が何ができるか考えてみようよ」と、監督に問われているかのようだ。そうした内省を促してくれるということも『猿の惑星:創世記』と『囚われた国家』(およびSF作品全般)の大きな魅力であり、やはり現実の世界が大変である今にこそ観てほしいと思える理由なのだ。
ちなみに、その『猿の惑星:創世記』には、まさに恐ろしいウイルスがパンデミックする“兆し”も示されているという、今に観るとさらにタイムリーな要素もあったりする。配信サービスのHuluで、続編の『猿の惑星: 新世紀』(2014)と『猿の惑星: 聖戦記』(2017)も鑑賞できるので、ぜひ合わせて鑑賞してみてほしい。
<文/ヒナタカ> 雑食系映画ライター。「ねとらぼ」や「cinemas PLUS」などで執筆中。「天気の子」や「ビッグ・フィッシュ」で検索すると1ページ目に出てくる記事がおすすめ。ブログ 「カゲヒナタの映画レビューブログ」 Twitter:@HinatakaJeF
1
2
ハッシュタグ


