株式投資でなぜドル円相場を見るべきか? 元日経新聞記者が実体験から考察
為替相場は両国の購買力平価を反映している
 外国為替レートは、基本的には「購買力平価」を反映して動きます。購買力平価とはそれぞれの国の通貨価値だと考えてください。
たとえば、ハンバーグ1個の値段がアメリカでは1ドル、日本では200円だったとします。この場合ハンバーグで計算した円ドル相場は1ドル=200円になります。2年後にアメリカではハンバーグ1個の値段が1.5ドルに上昇、日本では230円に上昇したとします。
このことは何を意味しているのでしょうか。アメリカでは、2年前なら1ドルで1個買えたハンバーグが今では1.5ドルないと買えません。ハンバーグに対してドルの価値が約33 %減価したことを意味しています。一方、日本では2年前に200円だったハンバーグが230円で買えます。ハンバーグに対する円の価値は13%減価となります。
ドルの価値が約33%低下したのに対し、円は13%の低下と少なく、その分ドルに対する円の値打ちが上がったことになります。この場合のドル円相場は約1ドル=153円になります。
実際の購買力平価は、個々の商品価格を比較するのではなく、国別に集計した企業物価指数(卸売物価)や消費者物価指数などマクロの物価指数の変化を比較することで購買力平価を決めます。為替相場は、基本的にはこの購買力平価を反映していると考えられています。
購買力平価の各国比較で自国通貨の価値が向上することは、基本的に望ましいことです。しかし輸出企業にとっては、自国通貨の価値が上がった分、輸出価格が高くなり、国際競争力上不利になるため、個々の企業ベースでは自国通貨安は歓迎されます。
外国為替レートは、基本的には「購買力平価」を反映して動きます。購買力平価とはそれぞれの国の通貨価値だと考えてください。
たとえば、ハンバーグ1個の値段がアメリカでは1ドル、日本では200円だったとします。この場合ハンバーグで計算した円ドル相場は1ドル=200円になります。2年後にアメリカではハンバーグ1個の値段が1.5ドルに上昇、日本では230円に上昇したとします。
このことは何を意味しているのでしょうか。アメリカでは、2年前なら1ドルで1個買えたハンバーグが今では1.5ドルないと買えません。ハンバーグに対してドルの価値が約33 %減価したことを意味しています。一方、日本では2年前に200円だったハンバーグが230円で買えます。ハンバーグに対する円の価値は13%減価となります。
ドルの価値が約33%低下したのに対し、円は13%の低下と少なく、その分ドルに対する円の値打ちが上がったことになります。この場合のドル円相場は約1ドル=153円になります。
実際の購買力平価は、個々の商品価格を比較するのではなく、国別に集計した企業物価指数(卸売物価)や消費者物価指数などマクロの物価指数の変化を比較することで購買力平価を決めます。為替相場は、基本的にはこの購買力平価を反映していると考えられています。
購買力平価の各国比較で自国通貨の価値が向上することは、基本的に望ましいことです。しかし輸出企業にとっては、自国通貨の価値が上がった分、輸出価格が高くなり、国際競争力上不利になるため、個々の企業ベースでは自国通貨安は歓迎されます。
為替レートは金利の変化などにも影響される
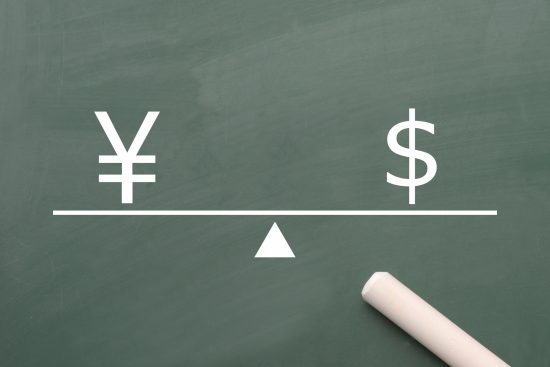 長期的に見ると、各国の購買力の違い(物価上昇の違い)が為替レートに影響を与えることに異議を唱える学者は少ないと思います。だが、為替レートに影響を与える要因はほかにもあります。たとえば、ある国の通貨供給量が他国よりも増えれば自国通貨安、実質所得が増える場合や金利が上昇すれば自国通貨高になる傾向が強まります。
この他、財政赤字が膨らみ債務危機に陥る、自国を巻き込むような戦争の危機が強まるなどの事態が予想されれば、自国通貨を売って安全な国の通貨に買い替えたいと思う人や企業が増えるため、自国通貨安になります。
円ドル相場の行方も、以上のようなさまざまな要因で変化するので、日米の物価・金利動向、財政収支・国際収支動向、雇用状況や企業業績などに目配りをしながら、中・長期的にドル円相場がどのような方向に向かいそうなのかを、自分なりに判断する力を養う努力が大切です。
とはいえ、前日のNY市場でドル円相場が円高に振れれば日経平均は下落、円安に振れれば上昇という傾向が、これまでの経験として観測されています。やはりNY市場の動きがチェックすべき主要な指標になります。
長期的に見ると、各国の購買力の違い(物価上昇の違い)が為替レートに影響を与えることに異議を唱える学者は少ないと思います。だが、為替レートに影響を与える要因はほかにもあります。たとえば、ある国の通貨供給量が他国よりも増えれば自国通貨安、実質所得が増える場合や金利が上昇すれば自国通貨高になる傾向が強まります。
この他、財政赤字が膨らみ債務危機に陥る、自国を巻き込むような戦争の危機が強まるなどの事態が予想されれば、自国通貨を売って安全な国の通貨に買い替えたいと思う人や企業が増えるため、自国通貨安になります。
円ドル相場の行方も、以上のようなさまざまな要因で変化するので、日米の物価・金利動向、財政収支・国際収支動向、雇用状況や企業業績などに目配りをしながら、中・長期的にドル円相場がどのような方向に向かいそうなのかを、自分なりに判断する力を養う努力が大切です。
とはいえ、前日のNY市場でドル円相場が円高に振れれば日経平均は下落、円安に振れれば上昇という傾向が、これまでの経験として観測されています。やはりNY市場の動きがチェックすべき主要な指標になります。
ハッシュタグ


